就労選択支援とは?なぜ必要なのか?デメリットも含めてわかりやすく解説します!
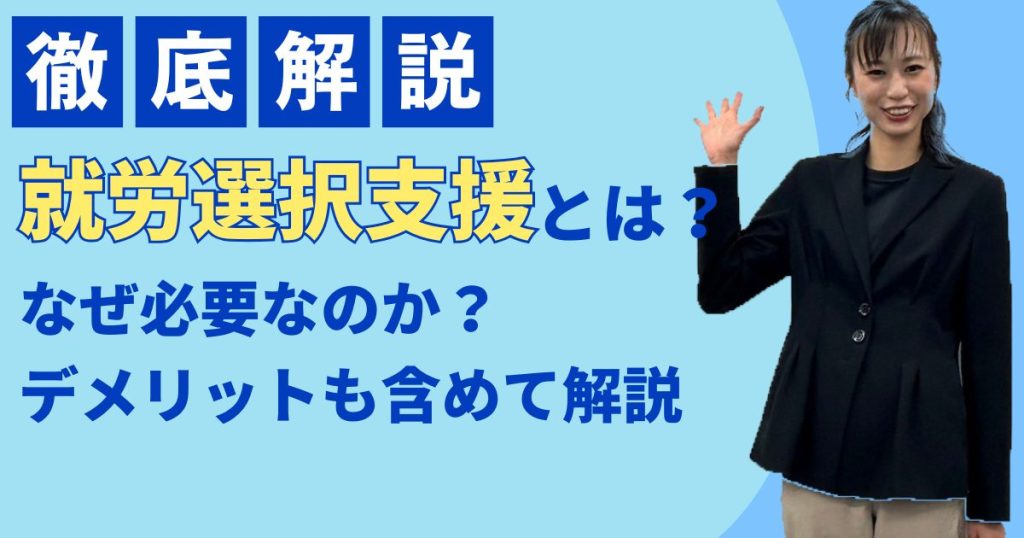
就労選択支援がついに令和7年10月より、就労継続支援B型の入所者を対象に開始されます。
- 「もう、就労B型には入れなくなるの?なぜ必要なの?」
- 「選択支援の利用勧められたけど、どこにいけば良いの?」
- 「どれくらいの期間の利用するの?」
など、様々な不安があるかと思います。
そこで、今回は就労選択支援制度について
実際の就労選択支援を令和7年10月より開始する事業所がわかりやすく解説します。
また、後半では利用者様だけでなく、報酬や指定要件など
事業者様向けにも解説しております。
この記事で、就労選択支援の全てがわかります!
また、こちらでは動画でも詳しく解説しておりますのでご覧くださいませ。
就労選択支援とは?わかりやすく解説【図解付き】

就労選択支援とは、利用者適切な就労系サービスを利用できるように
令和6年4月1日に施行
そして、令和7年10月1日より始まる新しい就労系サービスです。
新規に就労継続支援B型に入所を希望する方は原則、利用義務化されています。
(利用自体は、B型入所希望者以外も可能です。)
作業所に通うように、1ヶ月間(最長2ヶ月)の間、就労選択支援事業所に通って様々な作業をすることにより
どの就労系サービスがその人に合っているか?診断し、
その後、最適な就労系サービスを見つけます。
利用者は1カ月間(最長2カ月間)、就労選択支援事業所に通いながら
主に以下を行います。

就労選択支援では具体的に何をする?就労アセスメントの内容
では、具体的に就労選択支援に通って一体何をするのか?
最も重要視されるプロセスがこの就労アセスメント。
単なる職業訓練ではなく、「自分に合った働き方」を見極めるためのプロセスとなります。
以下が定められている基本的な就労選択支援の内容です。
実際の作業体験を通じた能力の評価
実際の職場に近い環境で、多様な作業(軽作業、事務補助、清掃など)を体験。
これにより、以下の点を客観的に評価します。
作業遂行能力: 指示の理解度、作業の正確性、集中力の持続時間、体力など。
対人スキル: 職員や他の利用者とのコミュニケーション能力、チームでの協調性など。
環境への適応力: 騒音や照明など、特定の環境下での働きやすさや課題。
専門家との面談による意思の整理
利用者本人と職員が、体験結果をもとに就労選択支援員と定期的な面談を行います。
希望や意向の明確化: どのような仕事に興味があるか、将来どのような働き方をしたいかを整理します。
必要な配慮の整理: 体調管理や休憩の取り方、職場に求める具体的なサポート内容を明確にします。
最終的にどの就労サービス・又は就労を行うか?判断
支援期間の終盤には、利用者本人・家族・相談支援専門員・ハローワーク担当者など、
複数の関係者が集まるケース会議を開きます。
このケース会議では主に
作業体験の結果や医療的な情報を共有や 集まった専門的な意見をもとに、
利用者に最も適した就労系サービス(就労移行支援、A型、B型)や一般就労への進路を具体的に検討します。
【アセスメント結果の活用】
これらのプロセスを経て、利用者の強み、課題、必要な配慮、適した進路を記載した就労アセスメント結果を作成し、本人に共有します。
この結果は、その後のサービス利用決定やハローワークでの就職活動において、重要な資料として活用され
この一連の支援により、利用者は自分自身を深く理解し、
「なんとなく」ではなく自身の能力や希望を正確に把握して就労系サービスや進路(一般就労など)を決定することができます。
就労選択支援の利用対象者と期間
次に就労選択支援の利用対象者ですが以下のようになります。
就労選択支援の主な対象者は、就労移行支援、就労継続支援A型、または就労継続支援B型といった就労系障害福祉サービスを新たに利用したい障害のある方です。
特に、新規に就労継続支援B型に入所を希望する方は、原則として令和7年10月1日より就労選択支援の利用が義務化されています。
また、令和9年4月1日より、
就労継続支援A型を利用を希望する方・就労移行支援を2年を越えて利用する方も義務化の対象となります。
さらに、以下の人も義務ではありませんが、利用対象に含まれます。
- 就労継続支援B型をすでに利用している方で、一般就労や就労継続支援A型への移行を検討したい方。
- 特別支援学校高等部に在籍する生徒で、卒業後の進路(就職または福祉サービスの利用)を具体的に検討したい方。
その他、就労系サービスの利用に関し、自身の適性や希望について客観的な評価と支援を希望する方。
B型入所希望者が義務化から外れる例外規定
就労継続支援B型への新規利用希望者のうち、以下のいずれかの条件に該当する場合は、就労選択支援を利用しなくてもB型サービスを受けることが認められています。
【利用者個人の状況による例外】
年齢や障害の程度、就労経験を考慮し、一般就労や他のサービスへの移行が非常に難しいと判断されるケースです。具体的には
・50歳に達している者
(就労選択支援はキャリアアップを目的としているため、50歳以上の場合は体力的な側面や、一般就労への移行が難しいという現実的な考慮がされる)
・障害基礎年金1級を受給している者
(重度の障害により、継続的な就労能力の向上や一般就労への移行が現実的に困難であると判断される)
・就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者
(過去に就労経験があるものの、加齢や体力の低下により、B型以外のサービス利用が難しいと判断される)
【地域的な要因による例外】
サービス提供体制がまだ十分ではない地域への配慮です。
・近隣に就労選択支援事業所がない場合
(地理的にサービスを受けられない場合)
・利用可能な就労選択支援事業所が少なく、利用するまでに待機期間が生じる場合
(サービス提供体制が追い付いておらず、待つことで就労開始が大幅に遅れる場合)
制度が始まって当分の間は、まだまだ事業所数も少ないため当分の間は
例外規定が多く適用されると思います。
就労選択支援の利用期間について
原則的な利用期間は1ヶ月間。最長期間で特に継続的な作業体験が必要と認められた場合は、2ヶ月間まで延長が可能です。
この短い期間で、集中的なアセスメントと意思決定支援を行い、その後の適切なサービス利用へとつなげることを目指します。
就労選択支援はなぜ始まった?背景について
ではなぜ、就労選択支援という制度が始まったのでしょうか?
一番の理由として、厚生労働省が掲げているのは
主に就労継続支援B型・A型の利用者に流動性のないことがあげられます。
具体的には、従来の就労系障害福祉サービスが抱えていた、
以下の2つの大きな課題を解決するために創設されました。
B型利用者のキャリアアップの停滞と「制度の谷間」の存在
既存の就労系サービス(特に就労継続支援B型)では、働く能力や意欲が向上しても、次のステップへ進む利用者が少ないという問題がありました。
B型事業所からの移行の停滞: B型は雇用契約がないため、比較的低い工賃で働き続ける利用者が多く、能力が伸びても就労移行支援や一般就労といったより高い目標へ向けてキャリアチェンジを図る機会が不足していました。
初期段階でのミスマッチ: 就労支援サービスを新たに利用する際、自身の適性や必要な配慮を十分に理解しないままサービスを選び、
- 「思っていたのと違った」
- 「自分には合わなかった」
という理由で早期にサービスから離脱するミスマッチが発生していました。
就労選択支援は、この「働きたいけれど、どのサービスが自分に合うのか分からない」又は「自身の能力を把握できず、今の現状に留まる」という制度の谷間を埋めることを最大の目的としています。
厚生労働省が掲げる「福祉から雇用へ」の流れの促進
厚生労働省は、障害のある方が能力や適性に応じて活躍できる社会を目指し、
「福祉的就労から一般就労へ」の流れをかなり強く推し進めています。
一般就労移行率の向上: 就労選択支援によって、利用者が自身の強みを明確に把握し、最適なサービスを選べるようになれば、結果的に就労移行支援やA型への移行が増え、最終的な一般就労への移行率が向上することが期待されます。
質の高い雇用の実現: 適切なアセスメントを経ることで、利用者は必要な配慮を明確にしたうえで就職活動ができるため、職場への定着率が高まり、より質の高い雇用が実現します。
このように、就労選択支援は利用者の主体的な意思決定を最大限に尊重しながら、
日本の障害者就労支援全体を、停滞から流動性のあるキャリアアップへと転換させるための新しい仕組みとして導入されました。
就労選択支援のデメリットについて
これまで就労選択支援の内容や制度創設の背景を見てきましたが、
果たしてこの制度にデメリットはないのでしょうか?
まだ始まっていないサービスのため、実務的には分かりませんが
現状、以下のようなデメリットが想定されます。
(※あくまでも当事業所が想定するデメリットです)
利用者の負担やプレッシャーが増える懸念
一番懸念されるのが、サービスを受ける利用者の皆さんへの影響ですね。
特に就労継続支援B型への入所を希望する方にとって、まず就労選択支援(アセスメント)の利用が原則義務化されるわけですから、
- 「いきなり試験を受けるみたいで緊張する…」
- 「働きたいだけなのに、なんでこんなに色々評価されなきゃいけないの?」
といった心理的なプレッシャーにつながる可能性があります。
短期間で結論を迫られる感覚: サービス期間は原則1ヶ月(最長2ヶ月)と短期間です。この短い期間で自分の適性を見極め、今後のキャリアを決定しなければならない、という焦りを感じてしまうかもしれません。
特に体調の波がある方や、自己理解に時間がかかる方にとっては、十分に検討する時間が取れない、というデメリットになる可能性があります。
地域によってはサービスの質にばらつきが出る恐れも
この新しい制度を担う事業所は、まだ全国的に数が少ない状況です。
そもそも、現時点で障害者雇用の求人数や就労移行支援などの一般就労への就職者数、ハローワークの能力でさえも地域で大幅な偏りがあります。
事業所不足による待機発生の懸念: 義務化されるB型希望者が増えた場合、地域の就労選択支援事業所の数が足りず、利用したくても待機しなければならない、という事態が起きる可能性があります。
アセスメント能力のばらつき: サービス提供の要件として「過去3年で3名以上の就職実績」が求められますが、実績があるからといって、中立的で質の高いアセスメント(評価)ができるとは限りません。
就労選択支援員の専門研修は始まったばかりで、事業所によってアセスメントの質や、関係機関との連携体制にばらつきが出てしまうかもしれません。
就労選択支援の実際の流れ
では、具体的に就労選択支援の利用の流れを見ていきたいと思います。
以下の、動画では
就労選択支援の利用イメージを実演しておりますので
動画でご覧になりたい方は以下よりYoutubeでご覧下さい。
1. 利用の相談と申請
就労選択支援を利用したい、あるいは利用が必要と判断された方は、まずお住まいの市区町村の窓口、または相談支援事業所に相談します。
申請のきっかけ:
新たに就労継続支援B型の利用を希望する場合(原則義務化)。
現行の就労系サービスの利用継続やステップアップを検討したい場合。
特別支援学校の生徒が卒業後の進路を検討したい場合。
相談を受けた市町村は、利用希望者の状況を確認し、就労選択支援の支給決定を行います。
2. 就労選択支援事業所の利用開始
支給決定後、利用者は指定を受けた就労選択支援事業所と契約し、サービスを開始します。
オリエンテーションと目標設定: 支援員と面談し、これまでの生活歴や職歴、そして「どんな働き方をしたいか」という本人の希望や目標を詳細に確認し、アセスメントの具体的な計画を立てます。
3. 就労アセスメント(評価)の実施
ここが就労選択支援の中心的なプロセスです。原則1ヶ月間、集中的に以下の活動を行います。
作業場面での評価: 事業所内の訓練・作業室や模擬的な職場環境で、様々な種類の作業(軽作業、データ入力、清掃など)を体験し、職業能力、体力、集中力、対人スキルなどを客観的に評価します。
自己理解の促進: 支援員は、作業中の様子や結果を利用者と共有し、「あなたが強みを発揮できたのはどんな時か」「課題を感じたのはどんな時か」といったフィードバックを通じて、本人の自己理解を深めます。
職場実習の活用: 必要に応じて、地域の企業や他の就労系サービス事業所での短期間の実習も組み合わせ、より実践的な適性評価を行います。
4. 多機関連携によるケース会議
アセスメント期間の終盤に、支援員、利用者、家族、そして必要に応じてハローワークや医療機関などの関係者が集まり、会議を開催します。
アセスメント結果の共有: 支援員が作成したアセスメントシートに基づき、利用者の強み、課題、必要な配慮事項を共有します。
進路の検討と決定支援: 各機関の専門的な意見を踏まえ、利用者が最も適した次の進路(就労移行支援、A型、B型、または一般就労)を主体的に選択・決定できるようサポートします。
5. 次のサービスへの移行
決定した進路に基づき、市町村に新しいサービスの支給申請を行い、就労選択支援は終了します。
以上が就労選択支援の想定される流れとなります。
まだまだ創設されたばかりのサービスのため、実務面でばらつきはあるかと思いますが
大まかにはこの流れになるかと思います。
特別支援学校の在学中の方の就労選択支援の利用
現在、特別支援学校に通っている方の就労選択支援の利用にも触れておきます。
特に現在、お子様が特別支援学校に通っている場合などは、進路面で大きな影響があるため気になる点かと思います。
特別支援学校(高等部)の在校生にとって、就労選択支援は卒業後の進路を早期から具体的に検討できるという点で、非常に重要な役割を果たします。
従来の就労支援サービスは卒業後に利用を開始するのが一般的でしたが、この制度は学校と福祉が連携し、生徒のキャリア形成を強力にサポートする仕組みとなっています。
支援の対象とと支援学校特有の柔軟な実施時期
就労選択支援は、特別支援学校の高等部の在校生全員が利用対象となります。
特別支援学校で就労選択支援を利用する際に特に注目すべきは、利用時期の柔軟性です。
従来の制度は主に3年生での利用が中心でしたが、就労選択支援は1・2年生の段階から必要に応じて利用することが可能です。これにより、時間をかけて進路を検討できます。
さらに在学中に複数回サービスを利用することも可能です。例えば、1年生の時に能力の基礎的なアセスメントを行い、3年生でより具体的な進路選択のためのアセスメントを行う、といった活用が想定されています。
学校が実施する職場実習のタイミングに合わせて就労選択支援を実施することもできます。
実習先での作業の様子や生徒の適応状況を、就労選択支援員がより専門的な視点から評価できるため、アセスメントの質が向上します。
支援学校と事業所の連携強化
就労選択支援を学校で活用するメリットは、生徒や保護者、そして学校の先生が、客観的な視点と福祉サービスの専門性を得られる点にあります。
就労選択支援員は学校の先生とは異なる立場で、生徒の職業能力や必要な配慮を客観的に評価し、アセスメントシートを作成します。
この客観的なデータは、学校の進路指導や保護者の皆さんが進路を決める際の揺るぎない判断材料となります。
さらに、前述の通り1・2年生でも利用が可能なため早期にアセスメントを行うことで、「卒業までにどんなスキルを身につけるべきか」
「卒業後すぐに就労移行支援を利用するのが良いか」など
福祉サービスを見据えた学校生活の目標設定が可能になります。
保護者の皆さんにとっては、在学中から専門的なアセスメントを通じて、お子さんの「働く力」と「意思」を深く理解し、卒業後に不安なく福祉サービスや就職へ移行するための大きな安心材料になるかと思います。
就労選択支援の利用料金は?
利用料金についても触れておきたいと思います。就労選択支援を利用する場合も、他の障害福祉サービスと同様に、世帯の所得に応じて月ごとに負担の上限額が設定されます。この上限額を超える利用料は、国や自治体が負担してくれます。
| 区分 | 所得の状況 | 負担上限月額 |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外(市町村民税所得割16万円以上) | 37,200円 |
就労選択支援の標準的な利用期間は1ヶ月(最長2ヶ月)と短いため、仮にサービス費用が1ヶ月で高額になったとしても、上記の上限額を超えて支払う必要はありません。
就労選択支援利用後の進路について
では、実際に就労選択支援を利用後に考えうる進路について解説しておきます。
主に以下の4つのパターンに分かれます。
1. 一般就労(企業への就職)
アセスメントの結果、利用者本人の能力やスキルが企業で働く準備が整っていると判断された場合、すぐに一般就労を目指す進路が選択されます。
就労選択支援で整理された「強み」「必要な配慮事項」を明確にしたアセスメントシートは、ハローワークや就労支援機関と共有され、就職活動や採用面接、職場への配慮依頼の際に活用されます。
移行先の支援: 就職後も、必要に応じて就労定着支援や障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)のサポートを受けながら、長く働き続けることを目指します。
2. 就労移行支援(一般就労に向けた訓練)
働く意欲はあるものの、一般就労に必要な知識やスキル、または生活リズムの安定に、あと一歩の訓練が必要だと判断された場合に選択されます。
就労選択支援で「一般就労への意欲と基礎能力はある」と確認されたため、就労移行支援ではより具体的で効率的な訓練に集中できます。期間は原則2年間で、ビジネスマナーやパソコンスキルなどの習得を目指します。
3. 就労継続支援A型(雇用契約ありの就労)
現時点では一般就労は難しいが、安定した環境で雇用契約を結び、最低賃金以上の給与を得ながら働きたいという希望があり、それに耐えうる能力があると判断された場合に選択されます。
A型は雇用契約があるため、給与を受け取りながら職業スキルや知識を習得できます。
ここでさらに能力が向上すれば、本人の希望に応じて再度、就労選択支援を利用して一般就労へのステップアップを検討することも可能です。
4. 就労継続支援B型(非雇用型・マイペースな就労)
体力や体調に課題があり、雇用契約を結ぶことは困難だが、自分のペースで無理なく生産活動を行い、工賃を得たいという場合に選択されます。
B型は、特に重度の障害がある方や、体調の変動が大きい方にとって、最も安心して利用できる働き方です。このサービスは原則、就労選択支援を経ることが義務化されるため、「B型で良いのか」をしっかり検討した上での納得感のある選択となります。
就労選択支援は、これらの進路の「振り分け」を行うものではなく、あくまで本人が進路を主体的に選ぶための支援です。利用者一人ひとりの希望や適性が尊重された上で、次のステップが決まります。
就労選択支援の運営について(ここからは事業者向け)
ここからは、主に相談支援事業者や就労継続支援B・A型、就労移行支援など
就労選択支援というサービスについて疑問がある方に向けて作成しております。
主に、指定要件や人員基準、そして報酬単価について解説していきたい思います。
就労選択支援はどこがやるの?実施主体について(指定要件)
それでは就労選択支援の実施主体についてですが、既存の就労系事業所がサービスを提供するには、
都道府県から「就労選択支援事業所」としての指定を受ける必要があり、
その際に満たすべき要件は他の就労系サービスと同様に定められています。
【実施主体となる事業所と満たすべき要件】
就労選択支援を実施できるのは、主に以下の既存の就労系サービス事業所です。
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援A型事業所
- 就労継続支援B型事業所
これらの事業所が、就労選択支援事業所として指定を受けるために満たすべき主な要件は、以下の通りです。
実績に関する要件(最も重要な要件)
過去3年以内に、当該事業所の利用者が新たに通常の事業所(一般企業)に合計3人以上雇用された実績があること。
または、これらと同等の障害者に対する就労支援の経験および実績を有すると都道府県知事等が認めた事業者であること。
人員に関する要件
就労アセスメントを専門的に行うための職員の配置が求められます。
就労選択支援員(原則1名以上):
必須: サービス管理責任者研修に加え、就労選択支援に関する専門の研修を修了している必要があります。
その他の従業員:就労選択支援のサービス提供時間を通じて、必要な数の従業員が確保されている必要があります。
設備に関する要件
利用者に対し、作業体験や相談を行うための適切な環境が求められます。
専用の区画: 事業の運営に必要な設備に加え、作業体験やアセスメントを実施するための十分な広さの場所が確保されていること。
設備・器材: 作業体験を可能にするための多様な作業内容に対応できる設備や器材が備えられていること。
運営に関する要件
サービスの公平性、中立性、そして質の担保に関する要件です。
中立性の確保: アセスメントの結果や提供する情報が、自事業所への囲い込みや特定のサービス利用に偏ることのないよう、公平かつ中立的な運営体制が求められます。
関係機関との連携: アセスメントを円滑に行うため、ハローワーク、医療機関、特別支援学校、他の福祉サービス事業所等との連携体制をあらかじめ構築しておくこと。
これらが、就労選択支援を運営する上での実施主体となる要件となります。
就労選択支援員について
前述の指定基準に登場した就労選択支援員について
主に国が行う就労選択支援員養成研修を受講することにより、
人員基準を満たす資格が発行されます。
すでに、就労選択支援員養成研修の募集要項は発表されているため
詳しくは各都道府県のページを参照下さい。
就労選択支援の報酬単価
就労選択支援の報酬単価について最後に触れておきたいと思います。
1. 基本報酬(サービス費)
就労選択支援の基本報酬は、原則として利用者の人数や支援内容に応じて日額単位で定められています。
基本サービス費(1日あたり): 1,210単位
この基本単位数に、地域ごとに定められた1単位あたりの単価(多くの場合10円)を掛けることで、1日あたりの報酬額が算出されます。
これは、1ヶ月間(20日間利用と仮定)で約242,000円相当の報酬が事業所に支払われる計算になります。
2. 加算・減算について
就労選択支援には、サービスの質や専門性を高めるための加算と、不適切な運営を防ぐための減算の仕組みが設けられています。
就労選択支援の主な加算・減算の報酬単価
| 区分 | 報酬単価(1日あたり) | 算定要件の概要 |
| 就労選択支援特別加算 | 150単位 | 厚生労働大臣が定める基準(質の高いアセスメントの実施体制、専門職員の配置など)を満たした場合に加算されます。 |
| 送迎加算 | 54単位 | 事業所が利用者に対して、自宅や居宅、または指定された場所までの送迎サービスを提供した場合に加算されます。 |
| 特定事業所集中減算 | 200単位の減算 | 就労選択支援の結果に基づかず、利用者が特定の就労移行支援事業所、または特定の就労継続支援事業所へ、80%を超えて集中して移行したと認められた場合に、基本報酬から減算されます。 |
〜就労選択支援についてのQ &A〜
- 就労選択支援は誰が利用できますか?
- 就労に悩む障がいをお持ちの方にご利用いただけます
- 就労選択支援の利用が必須なのは?
- 令和7年10月以降に就労継続支援B型を希望する方です。
- 就労選択支援はどこがやる?
- 指定を受けた就労選択支援事業所が行います。
- 就労選択支援の利用料金は?
- 所得に応じて、0円・9300円・37200円の場合があります。
- 就労選択支援の利用料金は?
- 所得に応じて、0円・9300円・37200円の場合があります。
- 就労選択支援 デメリットは?
- 体調の波がある方や、自己理解に時間がかかる方にとっては、十分に検討する時間が取れない事が挙げられます。
- 就労選択支援はなぜ始まったのですか?
- 主に就労継続支援B型・A型の利用者に流動性のないことから始まりました。
見学・説明会のご案内
当日、ご相談者様が指定されたお時間に、
大阪堺筋本町校・本町校・梅田校・大阪校・天王寺校
兵庫神戸校
お住まいよりお近くの校をご自由に選択の上、お越しくださいませ。

実際の見学会・説明会の風景です。
希望日時の方を以下の入力フォームよりご連絡ください。
(必須項目の入力をお願いします)
- 新着投稿 2026.02.13
- 新着投稿 2026.02.12
- 新着投稿 2026.02.12
- 新着投稿 2026.01.04
- 新着投稿 2026.01.04
- 新着投稿 2026.01.03
- 新着投稿 2026.01.03
- 新着投稿 2025.11.17
- 新着投稿 2025.11.10
- 新着投稿 2025.11.03













