就労移行支援でいじめはあるのか?実態と対処法を事業所目線で徹底解説
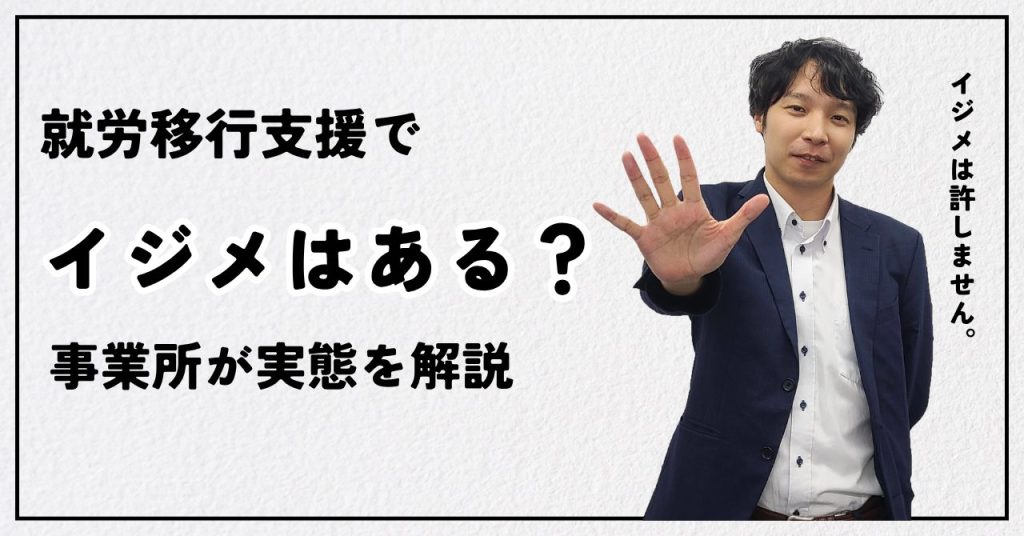
今回のコラムでは、かなり暗い話題とはなりますが、日々、就労支援の現場に携わる立場としても無視できない内容から
- 「就労移行支援におけるいじめの有無とその実態」
- 「いじめに対して具体的な対処法」
- 「いじめに合わない為の事業所選びのポイント」
- 「いじめに関する法律や支援制度」
- 「事例を元にその対処法などの解説」
を、私たちの目線から実際の所はどうなのか?もし、就労移行支援でいじめがあった場合はどうすればいいのか?などを網羅的に解説していきます。
就労移行支援でいじめは存在するのか?【どうしていじめが起こる?】
非常に残念なことではありますが、就労移行支援事業所内でのいじめは実際に存在します!
いじめと言うのは本来あってはならないものですし、当校ではもちろんそのような事例はありませんでした。
ただ、一部の就労移行支援でもいじめがあったと言うのは利用された方からもお伺いした事があるため事実としてあるようです。
何故、いじめが起こってしまうのか?ですが、就労移行支援などの福祉施設でいじめが起こってしまう原因は、大きく分けて2つではないかとお思います。
- 障害特性や性別・年齢・性格の不一致
- 就労支援職員の意識と環境整備の不備
などが、非常に大きな原因の一端ではないかと思います。
それでは、これらの二つをこれから一つずつご紹介していこうと思います。
就労移行支援の利用者間でのトラブルとその背景について【特性の不一致】
就労移行支援には様々な障がいや病気(精神障害や発達障害、知的障害や身体障害など)を抱えている方が利用しています。
様々な方が利用している中で、それぞれ障がいによって特性が変わってきますので、世間一般のよくあるパターンで言うならば、障がいの特性によるコミュニケーションの難しさが原因でいじめに発展してしまうケースがかなり多いのではないでしょうか?
また、いじめに至ってしまう背景には、年齢や性別・障がいの特性が原因と言うパターンはもちろんですが、一方で環境や日常生活のストレスが原因でいじめに至ってしまう事も社会ではよくある話なのではないかと思います。
そもそも、社会生活においての集団生活の中で「人と関わる(対人関係)に何らかの不安や不満・ストレスを抱えている」と言う方が、大多数であるこの日本ですが、その原因は様々です。
ですがまず、原因の一つとして特性やそれぞれの多様性から差別やいじめに発展しまう可能性はあるかと思います。
職員の意識と職場環境の影響【環境の不備】
就労移行支援でいじめが起こってしまう原因のもう一つは、その施設の環境整備が行き届いていない可能性が考えられます。
まずそもそも、就労移行支援でいじめが起こらないようにする為にもしっかりと職員が意識を高めておく事が重要です。
他にも、決して合ってはならない事ですが
あっては、ならない事ですが、例えば支援者自身も人間である為職場環境に不満があったり、日常生活において大きなストレスがあれば結果的にいじめを助長してしまう環境になってしまっていたりと
スキンシップとして放った何気ない一言がキッカケになってしまうこともあります。
ですから、私たち就労移行支援事業者自身がそういったことが起こらないように常に、気を配り雰囲気作りから徹底しておくことが重要となります。
就労移行支援でのいじめの種類と具体例
就労移行支援で起こるいじめの種類は以下のものが考えられます。
- 言葉によるいじめ
- 無視や排除行為
- 体力的な攻撃や嫌がらせ行為
このようにいじめと一言で言っても、いじめの種類は様々で多くあります。
就労移行支援に限らず対人関係がある場所では起こってしまう可能性が大いにあります。
これから、就労移行支援で発生するいじめの種類と具体例をいくつかご紹介していきたいと思います。
言葉によるいじめ
やはり1番多くなってくるのが、言葉によるいじめです。
言葉のいじめの中でも冷やかし、からかい、悪口など様々ありますが、この様ないじめは言われる方にとってはとても辛い事ですし、毎日続くと精神的にとてもダメージがありますよね。
言葉のいじめに対する具体的な例は・・・
- 容姿を馬鹿にされた
- 他の利用者同士の中で陰口を言われた
- 帰宅時(事業所外で)暴言を吐かれた
など
悪気が無く、つい言われた言葉で傷つく場合もあれば、完全に悪意のある言葉を吐かれる事もあるでしょう。
無視や排除行為
この無視や排除行為と言うのは、ある程度接点が無ければそこまで気にはならないかもしれません。
しかし、事業所内で挨拶をする仲や会話をする仲であれば、無視をされたり仲間外れにされた際に大きな精神的苦痛を味わう事になります。
無視や排除行為の具体例は・・・
- 挨拶をしても返答がない
- グループで取り組む活動内で輪に入れてもらえない
- 話しかけても避けられる
など
個人的に無視をされる事よりも、集団での無視や排除行為の方が多く、話し相手・相談相手が居ない中、
孤独感が強くなり雰囲気に耐え切れずに辞めてしまうケースがあるようです。
体力的な攻撃や嫌がらせ行為
このようないじめは少数にはなるのですが、暴力や威嚇行為・また自分の物を隠されるなどと言ったいじめになります。
叩く蹴るなどと言った暴力的ないじめは、誰かに言えば今よりも更にひどい仕打ちがあるんじゃないか?と恐怖により誰にも相談できないケースが多いです。
体力的な攻撃や嫌がらせの具体例は・・・
- 私物の教材や靴を隠された
- 頭や肩を叩かれた
- 作業中にしつこい妨害行為があった
など
このような暴力行為や嫌がらせは他の2つと違って、目に見えるいじめなので発見する事が出来れば対処する事が可能なのですが、こういった行為はやはり支援員の目の届かない所で、このようないじめが起こっている場合もあるでしょう。
また、付き纏いや、男女間でのトラブルもいじめと撮られる方も多くいらっしゃいます。
就労移行支援でいじめに遭遇した際の対処法4選
もしも、ご自身が就労移行支援を利用している中で、いじめを受けた場合またほかの誰かがいじめられているのを見かけた場合
一体どのように対処すれば良いのでしょうか?具体的には以下の4つがございます。
- 信頼できる職員へ相談する
- いじめの事実や記録を残す
- 他の利用者への相談や連携
- 事業所を変える
このような対処法が挙げられます。
直接、いじめている本人を注意することが出来ればいいのですが、いじめらている本人が相手に言う事は難しいでしょう。
なのでこれからいじめに対しての対処法をいくつかご紹介していきたいと思います。
信頼できる就労支援の職員へ相談
いじめが起こった場合や、いじめを目撃された場合は何よりもまずは職員へ相談しましょう。
自分の担当についてくれている支援員や信頼している支援員が居るのであれば、そちらの方に相談したり、サービス管理責任者への相談も検討してみましょう。
また、支援者自身からいじめを受けていると感じている場合も、その他の支援員や他の事業所に相談してみるのも良いでしょう。
支援者側はいじめ、つまり虐待を防止する義務がありますので、対処しない事は違法行為と言えます。
いじめの事実や記録を残すことの重要性
メモに『いじめが発生した日時』『発言や行為の内容』『状況』などを記録するようにしましょう。
このような記録は問題になった際に大きな証拠にもなるので思いだすのが辛いかもしれませんが、いじめが起きてからすぐに、できるだけ細かく内容を記録するようにしましょう。
現在はスマートフォンのメモや録音機能なども簡単に使えるので大事な証拠を残すためにも活用するようにしましょう。
他の利用者との連携
いじめの様な問題は絶対に一人で抱え込まないで下さい!本来は支援者がそのようなことが起こらないように対処すべきですが、そういった相談が難しい場合や
いじめとまでは言わないが、意見の言いにくい相手に少し諭してほしい場面もあるでしょう。
そういった場合にもし、信頼できる利用者さまが居らっしゃるのであれば、相談してみたりも良いかもしれません!
相談に乗ってくれたり、共感を得れるだけでも心の支えになります。
信頼できる仲間が一人でも居るのと居ないのとでは大きな差があります。
但:本来は就労移行支援の職員が責任を持って対処すべき事案ではあります。のでまずは優先して職員に相談を心がけましょう。
就労移行支援事業所を変える【転所する】
事業所内でトラブルが発生した際に、事業所を辞めてしまう人がおられます。
利用期間も定められているため辞めてしまうと非常に勿体ないので、事業所を変更も検討してみましょう。
環境を変えるのはメリットデメリットの両方がありますが、いじめから解放されるのであればメリットになるでしょう。
事業を変更する場合は職員や自治体に言えば変更する事ができるので、必ず相談するようにしましょう。
※就労移行支援のサービスを利用できる期間は原則2年間なので、期間に余裕がある場合は変更をおすすめします。
いじめの標的になりやすいのはどんな人?
まず大前提として、そもそもいじめそのものがもってのほかであり、どのような理由であれいじめる側が悪くなるのですが
その原因のほとんどが「他者との違い」を発端とした物が多い印象です。
そして、精神疾患や障がいをお持ちの方が利用する、就労系の通所施設では、その様な「人との違い」がより顕著に出る事があります。
例えば
- 極端な苦手やミスが目立つ
- 声が大きかったり言動が派手
- 清潔感が無くマナーが悪い
などが、考えられます。
また、精神疾患の症状によって「いじめられている」と感じてしまうケースもありますので、まずは担当の支援員に相談してみるようにするのが良いでしょう。
※補足:一般就労を行う場合、社会への適応も継続して長く働くコツの一つです。
なので、この様なポイントを抑えておき、つけ込まれないようにご自身で対策を行う事もとても大切です!
いじめを防ぐための就労移行支援事業所選びのポイント
まずはいじめを未然に防ぐためには事業所選びから始めましょう。
就労移行支援事業所は事業所によって利用者さんに対してのサポート体制は異なってきます。
就労移行支援を利用するにあたり、数ある就労移行支援の中でどこの事業所を選ぶべきか、とても迷うと思います。
いじめの事を心配している方に向けて、これからいじめを防ぐための事業所選びのポイントをご紹介していきたいと思いますので、
事業所選びの参考にしてみて下さい。
職員の質と事業所の文化を確認
事業所を選ぶ際に1番大事な事は、実際に事業所へ行き見学をすることです。
まずは事業所内の雰囲気を感じる事が大切です。
ホームページなどを見れば、写真で事業所内を載せている事業所はあるかもしれませんが写真では伝わらない雰囲気を感じましょう。
見学の際に、職員との面接の場が設けられますので、職員の話しやすさ、他の利用者さんと職員の接し方など
後は事業所の方針なども聞くようにしましょう。
事業所によっては支援員の育成に力を入れている入れている事業所もありますので、事業所にて支援員にいじめに対する対策を強化している事業所もありますので
事前にホームページなどで確認するか見学の際に直接聞くようにしましょう。
利用者の口コミや評判をチェック
事前にネットで検索すれば簡単に事業所の口コミを確認する事が出来ます。
このような口コミは実際に事業所を利用したことのある方が書き込んでいるので、参考にはなるとても有力な情報認なります。
この口コミを見て、いじめに関する事がもしも書き込まれているのであれば、いじめの内容・いじめに対する支援員の対応などを確認するようにしましょう。
いじめに関する事以外にも、『支援員の対応が悪い』や『サポート内容が悪い』などと言った内容が多く書き込まれている評判悪い事業所であれば利用するのを、できるだけ辞めておきましょう。
制度やサポート体制の充実度
いじめがあった際に、どこに相談すれば良いのかわからないまま、いじめを受け続けてしまうといったケースがあります。
そんな中で、事業所スタッフによる定期的な面談を行っている事業所や相談制度・第三者相談窓口などを設けている事業所もあります。
これはいじめに関わらず、何か事業所内で発生したトラブルを相談したり、就職に対する相談する窓口でもあります。
このように、何か相談をしたい時に、いつでも利用できる専用の窓口などがあれば、いじめにあった時にでもすぐに相談に行ける場所を把握できるので早急に対処できます。
後は利用者さんに対して担当のスタッフを付けることで、信頼関係を強くしてなんでも相談できる相手として接する事が出来るようなサポート体制を行っている事業所もあります。
就労移行支援でいじめ問題を解決するために
いじめを無くすためには就労移行支援事業所側が解決策を考えたり、いじめ防止に力を入れなければなりません。
いじめが発生してから対策をするのでは遅いので、未然に防ぐことが大事です。
既に対策を行っている事業所は多くあるのですが、これからいじめ問題を解決するために必要な事をご紹介していきたいと思います。
スタッフの研修と意識改革
1つ目は利用者さんに直接関わるスタッフの研修と意識改革です。
スタッフには、障がいの特性に対する理解を始め、トラブルが発生した際の対応マニュアルなどを覚えることでいじめに対しての対応方法などを身に着けさせることが必要です。
少しでもスタッフのいじめやトラブルに対しての意識が高くなれば、いじめを未然に防いだり、いじめに気付く事ができるでしょう。
そして、もしも利用者さんからいじめの相談をされた時には、他の事業所内スタッフと共有する事で迅速な対応を行うことが出来ます。
利用者同士のコミュニケーション促進
事業所内でコミュニケーションスキル向上のトレーニングの一環でSST(ソーシャルスキルトレーニング )やワークショップを行っています。
このようなトレーニングで十重要な部分は『自分の思った意見を言う』『相手の発言したことを理解する』と言った点です。
自分の言う事が全て正しいと思うのではなく、話し合いの中で、相手の言った事を聞いて理解する事も大切なのです。
社会に出てからも人とのコミュニケーションは必要ですし、話し方・スピード・トーンも印象ではとても大事です。
就労移行支援では、その辺りを練習できるので改善できる環境でもあります。
利用者さん同士のコミュニケーションのトレーニングで相手の気持ちを配慮できるようにしましょう
いじめの問題に関する法律と支援制度
それではこのいじめに関する問題ですが国の定めではどうなっているのでしょうか?
実は、障害のある方への差別と言う取り扱いで「障害者虐待防止法」「障害者差別解消法」と言うもので厳しく明示化されています。
| 【障害者虐待防止法】 |
障害者への虐待を禁止し、早期発見や通報義務が事業所側には義務付けられています。 いじめも状況によってはこれにあたります。 |
| 【障害者差別解消法】 | 障害のある方に対する不当な差別やいじめなどを禁止し、社会参加の上で合理的配慮の提供を求めると言ったものです。 |
就労移行支援を利用されている方の場合でれば、上記の「障害者虐待防止法」がより身近になってくるかと思います。
また、事業所側に相談ができない場合の相談窓口としては
- 市区町村の障害福祉窓口
- 社会福祉協議会
- 運営適正化委員会
- 弁護士
などが挙げられます。
福祉施設などをご利用の場合でもし、利用者間ではなく、職員からのいじめがという最悪のケースの場合は上記のような
相談窓口へとまず、相談する事をおすすめ致します。
(※そもそも、就労支援施設などの福祉施設において、職員が利用される方にいじめや不適切な言動を行うのは以ての外です。
もし、辛い思いをされている方がいらっしゃれば我慢せず適切な窓口への相談をおすすめいたします)
それでは、次にそれぞれの法律について簡単に概要をご説明いたします。
障害者虐待防止法の概要
それではまず、障害者虐待防止補の概要を見ていきましょう。
主に以下の、厚生労働省の資料の条文にあたる内容から「いじめ」の内容が「虐待」認められた場合厳格な処分が言い渡されるといったものとなります。
具体的な、厚生労働省の定める虐待の定義は以下の通りです。
障害者虐待防⽌法 第2条第8項 この法律において「使⽤者による障害者虐待」とは、使⽤者が当該事業所に 使⽤される障害者について⾏う次のいずれかに該当する⾏為をいう。
【⾝体的虐待】
⼀ 障害者の⾝体に外傷が⽣じ、若しくは⽣じるおそれのある暴⾏を加え、⼜は正当な 理由なく障害者の⾝体を拘束すること。
【性的虐待】
⼆ 障害者にわいせつな⾏為をすること⼜は障害者をしてわいせつな⾏為をさせること。
【⼼理的虐待】
三 障害者に対する著しい暴⾔、著しく拒絶的な対応⼜は不当な差別的⾔動その他の障害 者に著しい⼼理的外傷を与える⾔動を⾏うこと。
【放棄・放置】
四 障害者を衰弱させるような著しい減⾷⼜は⻑時間の放置、当該事業所に使⽤される 他の労働者による前三号に掲げる⾏為と同様の⾏為の放置その他これらに準ずる⾏為 を⾏うこと。
【経済的虐待】
五 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。
とありますので、このいずれかに抵触する場合は
事業所側には届出の義務があり適切に対応を行わない場合は、厳しい処分が下されます。
もしこのような、事実があった場合には市区町村への通報を行うことがここに記載されています。
障害者差別解消法の概要
こちらの障害者差別解消法に関しては、主に職場での障害者差別が主な取り扱いになります。
具体的に条文から解説するとかなり複雑になりますので、結論から分かりやすくご紹介いたします。
- 不当な差別的取扱いの禁止
- 合理的配慮の提供
となっていいます。
たとえば「不当な差別的取り扱い」であれば、
障がいがあるという理由で、サービス提供の拒否や制限をすることや、条件をつけることなどが含まれます。
より具体的な、内容で言うと障がいのある方の受付の対応を断る!障がいのある方から話しかけたり質問されたりしているのに、介助者の方だけに回答を行う、そもそも、障がいのある方に対してサービスを提供しないなどがこれにあたります。
そして、「合理的配慮」であれば、
2024年4月1日より障害者差別解消法で合理的配慮の提供が定められていますので
合理的配慮の提供では、「障がい者から配慮を求められたときに、過度の負担にならない範囲で、合理的な配慮を行う」とされています。
この過度な負担がと言う部分が非常にアバウトで分かりにくい面もありますが、双方の合意の元と言う点が非常に重要になってきます。
これを会社側が一方的に無視すると、この障害者差別解消法に抵触してくる可能性があるといったものです。
もし就労移行支援で実際にいじめがあったら?【体験談を元に解説】
それでは、最後に当校での実体験ではありませんが
利用頂いた方の過去の体験やネットで目にした、内容
その他の噂といった物から実際の事例といじめられたと言う方がとった対策
さらには、そういったいじめが起こらないように事業所などがとっている対策についてご紹介していきます!
いじめに対処された方の体験談
以前、就労移行支援事業所を利用されていた際に
職員から酷い言葉を掛けられたり、叱られたりと
いじめにあった経験があると言う方の対処法として
まず、医師や相談支援専門員などに相談をされたそうです!
そこで、他の事業所への転所を提案され思い切ってそれを相談支援専門員の方経由で、
その事業所のサービス管理責任者へと伝えて頂き無事に転所されたと言う事をお話しされていました。
当事は嫌なスタッフがいる事で、通所も安定せずそれに対しても「通所できないと、就職できませんよ!」と強い言葉をかけられ意欲も低下してしまっていたそうです。
今では、移行支援事業所を変えた事で担当支援員とも信頼関係を築き、就職活動にも意欲的に取り組まれているようで私たちもとても安心しております。
その方からのアドバイスとしては、いじめに苦しまれている方は
役所や相談支援、事業所の他の職員など誰でも良いのですぐに相談し
改善しなければ、利用期間を無駄にしないためにもすぐ転所を検討した方が良いとおっしゃっていました。
就労移行支援事業所側でいじめが起こらない対策をされている事例
そもそも、このような事が起こらないために
私たち就労移行支援事業者側がしっかりと対策をしなければなりません!
例えば、先ほどのような職員が利用者様へと言うのは以ての外ですが
利用される方同士でのトラブルなどは、起こる可能性がありますよね!?
例えば
- 利用される方同士の男女間のトラブル
- そもそも好き嫌いと言った人間関係のトラブル
などが起こりうるパターンかと思われます。
そこで、まず当校では
普段から担当職員が気を配る事はもちろんの事ですが
少しでも異変を感じたら、すぐに聞き取りを行ったり
不穏な空気を感じたら、席や空間をわけるといった配慮を心掛けております。
他にも、男女間や特性上人に執着してしまう方でトラブルと言った事も中には御座いますので
予め、事業所では個人間の連絡交換を禁止するであったり、なにかトラブルがあれば再発防止策を徹底するために
その都度、担当や席の変更、通所の時間や日程の調整、迅速な聞き取りなどの対策を行なっております。
また、一方的に片方がそのような事を行なっている場合には、厳重な注意などもやむ無く対応するケースも中には御座います。
あくまで、一例にはなりますがこのような対策が事業所で行なっている対策の事例となります。
就労移行支援といじめ・まとめ
これまで、就労移行支援でのいじめについて、どのようないじめがあるのか?
いじめを受けた時に誰に相談するべきか?などいじめに関する情報やいじめを受けた時の対処法などをご紹介してきました。
いじめに関してご紹介してきましたが、厳しく処分が行われますので就労移行支援でのいじめは滅多にないものであると考えて良いでしょう。
各事業所でイジメに関する防止対策は行われていますし、利用者さんもいじめをするような方も基本的にはいらっしゃいません。
なので、いじめ自体は滅多に無いものだと思ってもらって大丈夫です。
しかし、実際にいじめは有るのは有るので、もしもご自身がいじめを受けた、あるいは、いじめられていると感じたのであれば、必ず信頼できる人に相談するようにしましょう。
いじめが原因で就労移行支援の利用を辞めてしまう様な事の無いように、対策を取っていきましょう。
見学・説明会のご案内
当日、ご相談者様が指定されたお時間に、
大阪堺筋本町校・本町校・梅田校・大阪校・天王寺校
兵庫神戸校
お住まいよりお近くの校をご自由に選択の上、お越しくださいませ。

実際の見学会・説明会の風景です。
希望日時の方を以下の入力フォームよりご連絡ください。
(必須項目の入力をお願いします)
- 新着投稿 2026.02.13
- 新着投稿 2026.02.12
- 新着投稿 2026.02.12
- 新着投稿 2026.01.04
- 新着投稿 2026.01.04
- 新着投稿 2026.01.03
- 新着投稿 2026.01.03
- 新着投稿 2025.11.17
- 新着投稿 2025.11.10
- 新着投稿 2025.11.03













